
お月見(十五夜)
十五夜は、中秋の名月、芋名月とも呼ばれているお月見の日です。
お供えするのは、里芋、月見団子、すすき、秋の七草などの草花です。
十五夜にはお子さんと一緒に、月見団子を作ったり、秋の七草探したり、かぐや姫の絵本を読んだりして過ごしましょう。
中秋の名月です
十五夜は、中秋の名月とも呼ばれる代表的なお月見の行事です。
いつなの?
ところであなたは、いつ行われるのか、何月何日か正確な日付をご存知でしょうか?
スーパーマーケットなどでは「お月見フェア」などをやっていることがあるので、秋頃かなと、おおよその時期は分かっている方が大半でしょう。しかし、日付までは分からない方も多いのではないでしょうか。
かくいうサイト管理人もかつては、「お月見の行事って、年に何回もあるんだっけ?」という状態でした。
春夏秋冬いつの夜に見上げても、月は美しく魅力的ではありますが、これでは、ぜんぜん風流じゃないですよね(笑)
実は毎年日付が異なります
十五夜がいつなのか、その肝心な日付ですが、旧暦の8月15日です。
ここで留意点。旧暦は毎年日付が変わります。今年は新暦のいつにあたるのか、カレンダーでチェックしましょう。
ちなみに近年は次の日程となっています。
- 2016年(平成28年)は9月15日
- 2017年(平成29年)は10月4日
- 2018年(平成30年)は9月24日
満月だけではありません
旧暦8月15日(十五夜)の日程、ばらつきがありますよね。
あまり天体に詳しく無い方でも、年によって「月の満ち欠け」が若干異なる事は、なんとなく想像出来るのではないでしょうか。
そうなんです。厳密には完全な満月ではない年が結構あるんです。
でも、「今年の十五夜は満月じゃないから、お月見や~めた」は、ちょっと無粋です。
その時々、いつでも月は美しい表情をしています。お子さんに分かりやすく説明するなどして、豊かなひと時を過ごしましょう。
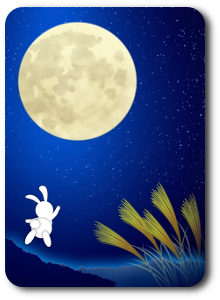
別名「芋名月」とも言います
十五夜には、「中秋の名月」の他にも別名「芋名月」という呼び名があります。
これは、里芋をお供えすることに由来しています。和菓子にありそうな、ちょっと美味しそう名前ですよね。
なぜ芋なの?
では、なぜ芋なのかというと、この行事(お月見)の発祥の地、中国に由来します。
昔の中国では、ちょうど里芋の収穫時期だったために、里芋をお供えしていたそうです。また、里芋は、親芋、子芋とどんどん増えて行くことから、子孫繁栄の縁起物という意味もありました。
秋に行われる理由は?
月は一年中見ることができます。満月も季節を問わず見ることができますよね。
では、なぜ「中秋の名月」と言われるように、秋にお月見が行なわれるのでしょうか?
それには、2つの大きな理由が考えられます。

一つ目の理由:月の角度
実は、満月は季節によって高度が変わります。最も高いのが冬で低いのは夏です。
また、見上げやすい角度になるのは春と秋とされており、秋の方が空気が澄んでいて空がより高く広く感じられます。
よって、輝く月がよく見えるということから、秋の真ん中、つまり中秋が名月とされるようになったのだそうです。
二つ目の理由:農作物の収穫時期
時期的に稲など農作物の収穫時期と重なることも、古来より秋にお月見の行事がなされた大切なポイントと言えます。
収穫したばかりの米などを「お月さま」に供え、収穫の感謝を表したということです。
十五夜のお供え、飾り、行事食
里芋、団子、秋の草花などが伝統的・代表的なものとなります。
お子さんをはじめ、ご家族で一緒に楽しみながら用意してみてはいかがでしょう。
里芋料理「衣かつぎ」
「衣かつぎ」は、里芋をゆでて、上半分の皮をむくだけの簡単な料理なので、家庭でも簡単に作れるでしょう。お子さんと一緒に作ってみるのも楽しいですね。

月見団子
ポピュラーであり、誰もが真っ先に思い浮かべるお供え物、行事食と言えば月見団子でしょう。
月に見立てて、まん丸に作った団子を十五個お供えします。
衣かつぎよりも簡単に作ることができますので、小さなお子さんでも一緒に作れますよ。
知人によると、小さな頃から毎年お母さんと一緒に月見団子を作ったものだそうです。白玉粉に豆腐を少し混ぜるのがコツで、 そうすると冷えても固くならないとの事。自分で作ると沢山食べられるのも、子供心に嬉しかったそうです。

すすき、秋の草花
秋の草花を飾りましょう。とりわけすすきは、月見団子とベストマッチします。
すすきは、垂れ下がる形が稲穂に似ており疑似的・代替的な役割を果たします。そして魔除けの意味もあります。
秋の草花は、お子さんと一緒に探しに行くと、色々な発見があって面白いでしょう。秋の七草を飾るのもおすすめです。
秋の七草について
秋の七草は下記の植物です。
- 萩
- 尾花(すすき)
- 葛
- 瞿麦葛
- 女郎花
- 藤袴
- 桔梗(朝貌)
山上億良が詠んだ和歌に由来します
万葉集に多数撰ばれている等、奈良時代を代表する歌人である山上億良が、次の和歌を詠んでおり、それに由来するとされています。
秋の野に 咲きたる花を 指折りかき数ふれば 七種(ななくさ)の花
萩の花 尾花(おばな)葛花(くずはな)瞿麦(なでしこ)の花 女郎花(おみなえし) また藤袴(ふじばかま)朝貌(あさがお)の花
十五夜とかぐや姫
昔から親しまれているお話にも、十五夜が登場するものがあります。
代表的なお話は、「かぐや姫」です。

竹から生まれたかぐや姫は、最後に月に帰っていきますね。月からお迎えが来た時は、眩くてみんな目が開けていられなかったそうです。この眩い満月の日が、十五夜でした。
という事は、かぐや姫は、秋の頃に月に帰って行ったのですね。中秋の名月を見ながら、お子さんと一緒にかぐや姫のお話を読むと、情景がよく伝わって話が弾むでしょう。
このコンテンツに関連するページ
*本ページの概要・情報は変更される事があります。
By Happie (Updated )














