
お七夜でお祝い
お七夜は、生まれてきた赤ちゃんの初めてのお祝いです。
お七夜は命名の儀式であり、そして産婦の回復祝いを兼ねています。
子供の健やかな成長を祈願し、会食の食事しながら幸せなひと時を過ごします。
命名の儀式を行います
お七夜の行事においては、赤ちゃんを、ごく近しい身内に「新たな一家の一員」として、お披露目する意味合いがあります。
メイン・イベントは、この尊い「いのち」への、「命名の儀式」です。

現行の民法では、新生児は、生後14日以内に、出生届を提出する規則です。
大切な命名。提出期限ギリギリまで、どんな名前にしようかとじっくりと熟考する方もいるでしょう。
今は、キラキラネームとか、独創的な名前も増えていますね。
この世に生まれて7日目、古式ゆかしいお祝いの日に、名前を授けてあげるのも良いものです。
命名書の書き方
命名書は、正式には、奉書紙と言われる巻物状の用紙に記すしきたりです。
最近では、半紙で略式の命名書を書くケースが多いようです。
半紙は白色のものが伝統的ですが、現代では色や模様が入った用紙もあります。
書き方は何通りかあります。では、その例をご紹介しましょう。
- 例その1
-
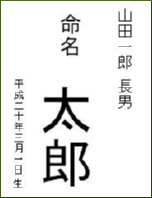
半紙の中央上部に「命名」、
その下に「名前」、
右側には「親の氏名」(両親連名でも可)、「続柄」、
そして、左側には「生年月日」。 - 例その2
-
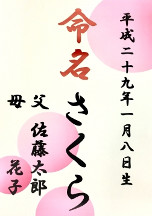
半紙の中央上部に「命名」、
その下に「名前」、
右側には「生年月日」、
そして、左側には「親の氏名」。 - 書き方のポイント
-
和式の筆記用具、墨と毛筆(あるいは筆ペン)で書きます。
(マジックやサインペンでは風情がありませんよね?)
基本的には、名付け親(名前を付けてくれた人)が筆を取ります。
(パパママではない場合、事前にお願いしましょう。)
大切に保管しましょう
命名書は、神棚、床の間、あるいは部屋の壁(赤ちゃんの枕元や近くが望ましいと思います)に貼り、床上げが過ぎるまで、あるいは出生届を提出するまで飾っておくのが一般的です。
その後は末永く保管しておきましょう。子供さんが大きくなった時に見せてあげると、感動的ではないでしょうか。
命名書と合わせて、手形、足型などを記念に取る方や写真、動画を撮る方が増えています。
「お七夜」に関する「保存アルバム」等のグッズやサービスもあります。
食事(祝い膳)について
赤ちゃんのお披露目、命名式を一通り終えた後に会食となります。
お七夜での食事、祝い膳の伝統的な定番料理は、赤飯と尾頭つきの焼き魚です。
焼き魚については、地方によって異なる場合もあるようですが、お祝いごとで用いられるおめでたい魚の代表格と言えば、やはり 鯛でしょう。それにしても私たち日本人は、鯛が大好きですね。(その他、伊勢海老や蛤なども好まれます。)
出前をとる場合
和式の行事なので、ピザや中華料理といった外国系のものよりも、お寿司やお弁当などの、純和食系のお食事のほうが合っているでしょう。
また、ケータリング(仕出し)専門店では、お七夜の祝い膳を提供しているお店もあります。

ところで赤ちゃんは、もちろん、まだ食事が出来る時期ではありませんよね。
食事に関する赤ちゃんのお祝いとしては、生後100日前後に行われる、「お食い初め」があります。
招待を受けた場合
お七夜に招かれた場合には、一般的には出産祝いを贈る事が多いです。
たとえばお金を贈る時は、赤白の水引を付けた熨斗(のし)に入れます。
表書は「御祝」、「御命名お祝い」などとし、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

お七夜の内祝いについて
当日、招待客から贈り物を頂戴した場合、会食の食事を、内祝い(お返し)とします。
名付け親になって頂いた方や仲人さん、平素大変お世話になっている方など大切な方たちには、謝礼やお祝い返しをする場合があります。この場合、赤ちゃんの名前(命名書)を添えて贈ります。
なお、贈り物を頂いた方の中で、会食にお招きしなかった方(欠席された方)に対しても、お祝い返しをしましょう。
※ご参考:内祝いのきほん
このコンテンツに関連するページ
*本ページの概要・情報は変更される事があります。
By Happie (Updated )







