
お盆
お盆は、日本人にとって大切な行事です。仏教の盂蘭盆会と日本古来の先祖祀りの信仰に由来します。
お盆の日程やしきたりは、地域により異なりますが、多くは8月13日からの4日間に行われます。
お墓の掃除をして盆棚を作り、迎え火、盆踊り等を催し、先祖や精霊を迎えます。
目次(全4ページ)
- 由来や意味(当ページ)
- お盆のスケジュール
- 盆飾り(盆棚の飾り方)
- お盆にまつわる有名な行事
お盆の由来
そもそも、お盆は何に由来するのでしょうか?
ご先祖様を慰めるということから、なんとなく宗教的な儀式では?と想像がつくかもしれませんね。
その通り。元々は仏教行事と古代信仰に由来しています。
- 盂蘭盆会(うらぼんえ)(「盂蘭盆経」に基づく行事)
- 土着の民間信仰(日本に古来より存在するもの)
この2つの行事・信仰が結びついて、現在のお盆が形作られていったと考えられています。
盂蘭盆経とは?
中国で編まれた偽経(説話)が起源とされる盂蘭盆経。日本に伝来後、宗派によりアレンジが加えられているようです。
あらすじ的に簡単に要約すると、次のようなお話になります。
-
母親が地獄(餓鬼道)に落ちていた・・・
お釈迦さまの弟子、目連尊者(もくれんそんじゃ)は、母親が死後の世界で苦しんでいることを知ります。
地獄(餓鬼道)に落ちており、食べ物が食べられなくなっていました。
母親は生前、自分の事しか考えておらず、また人の為に施しをしない等により、重い罪を背負っていたのです。
-
お釈迦様に相談する
ひどく胸をいためた目連尊者は、何とか母を助けられないものか、お釈迦様に相談しました。
-
お釈迦様より助言を得る
「7月15日に、多くの供物を捧げて盛大に全力で供養すれば、その功徳によって母親は助かるだろう」
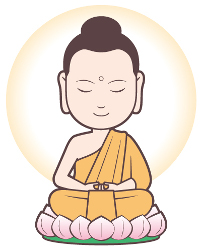
-
目連尊者、助言に従う
お釈迦様の助言に従い、目連尊者は大供養を行ないました。
すると、母親は地獄から極楽へ行くことが出来た(つまり往生した)のだそうです。
この説話にちなんで、仏教では先祖の霊を慰める「盂蘭盆会」が行なわれるようになりました。
盂蘭盆会がお盆の正式な名称であるとお考えの方も少なくないようです。
日本の古代信仰との関係

お盆の由来と慣習化については、日本土着の古代信仰も関係しているとされています。
日本の古代信仰では、初春と初秋の満月の日にご先祖様を迎えるというものがありました。
旧暦は月にのっとったカレンダー(日程)であるため、15日は満月となります。
そこで、7月15日の満月の夜、明るい月に照らされながらご先祖様はお帰りになる、という信仰が昔からあったのです。
行事の持つ意味
お盆は何のための行事?
ここまで読まれた方は、もうお分かりでしょう。
お盆とは、ご先祖様や精霊、無縁仏をお迎えし、もてなして慰める行事です。
そのために、盆棚を作り、迎え火をたき、盆踊りを行い、地域によっては灯籠を流したりします。

日頃、命の大切さ、生きる意味について考える機会はそう多くはありません。特にお子さんは、まだあまり命の重さを体感するような経験はされていないことでしょう。
お盆は、ご先祖様を偲ぶと共に、生きていること、生かされていることに対する感謝の気持ちを育てるのに良い機会です。
また、目連尊者の母親が地獄に落ちた理由が、「自分のことばかり考えていた」ことにも注目すると良いですよね。自分のことだけでなく、周りにも気持ちを配れる大人に育って欲しいものです。
お盆の過ごし方
子供さんと行事のしきたりや装飾品の意味などを話しながら、家族で一緒にお盆の準備をするのは、とても良い事だと思います。

少し思い出話をさせて頂くと、筆者の家では、お盆には家族みんなでお寺(菩提寺)へ行き、寺内の霊園にてお墓参りをする習慣がありました。
そのお寺には「地獄」が描かれた絵巻物が飾られていました。恐ろしい鬼たちが跋扈(ばっこ)する地獄は、幼い頃、子ども心に本当に恐ろしかったです。
そして、母親から「悪い事をすると、地獄に落ちてしまうのよ」と言われて、自分の言動を振り返り、悪い事はしないようにしようと固く思ったものです。
お盆の時期には、それにちなんで、地獄や極楽、おばけの本などをお子さんと読むのも良いかもしれませんね。
お盆はいつ?
「盆と正月が一緒に来たよう」ということわざがあるように、お盆は日本人にとって大切な行事です。
社会人になって働き始めてからも、お正月とお盆には長期のお休みを取るという方も多いのではないでしょうか。
では実際にいつ行われるのか、実は地域によって実施する日が違います。日本全国、いっせいにお盆を迎えるわけではないのですね。
- 最も多くの地域で行なわれる時期は、8月13~16日の4日間です。
- 東京や静岡、金沢の一部の地域では7月13~16日に行われます。
- 東京多摩地区等、ごく一部の地域では、7月1日から月末までの1ヶ月間続きます。
- 沖縄では旧暦の7月13~16日に行なわれています。
お盆の話をするときは、時期に食い違いがないように、少し注意したほうが良いケースがあるようですね。
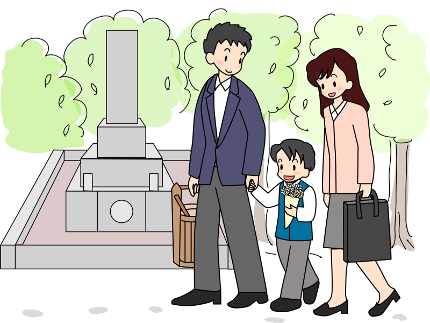
地域により時期に違いがあるのは、農業と関係しています
元来は、旧暦の7月13より16日の期間にて行なわれる行事でした。
そして、明治時代になって新暦が使われるようになると、お盆も新暦に改められることになりました。
しかし、新暦の7月では農業の繁忙期と重なってしまいます。そこで、多くの地域では一ヶ月遅らせることにして、ゆっくりとお盆を迎えるようになったのです。
お盆に関連するページ
*本ページの概要・情報は変更される事があります。
By Happie (Updated )




