
敬老の日
敬老の日は、年長の方たちを大切にして敬う思いから、その長寿を祝う国民の休日です。
本ページでは、敬老の日の意味や由来についてご紹介しています。
敬老の日の意味
敬老の日は、皆様ご存知のように「呼んで字の如く」の意味となります。
すなわち、その主旨は、
この文言は、「国民の祝日に関する法律 第2条」に定められている条文です。
「母の日」「父の日」または、還暦等の「長寿のお祝い」のように、「年長者の方をお祝いする日」は幾つかありますが、国民祝日として制定されているのは、唯一、敬老の日のみです。

私が子供の頃は、祝日は固定されていて毎年9月15日でしたが、祝日法が改正され、2003年度よりハッピーマンデー制度が導入されて以来、9月の第3月曜日が敬老の日になっています。
ちなみに2019年(令和元年)は、9月16日月曜日です。
由来やエピソード
記念日や祝祭日には、西欧由来や中国から伝わってきたものが数多くあります。
でも、敬老の日に関しては、完全な「日本のオリジナル」と言えるようです。
もともとは、ある地方の行事でした
そもそもの由来は、1947年に兵庫県の野間谷村(旧八千代町。現在の多可町。)が、「としよりの日」 として村独自の祝日を考案し、お年寄りを敬い大切にしようと敬老会を開催したのが始まりだそうです。
自分の家の祖父母などの長寿者だけではなく、その地域の全てのお年寄りを敬い労わろうとする発想が素晴らしいですね。
全国に広まり国民祝日へ
そして、それは良い事だと、周囲の市町村も呼応したのでしょう、1950年代頃には、兵庫県全域で行われるようになりました。
やがて「としよりの日」のコンセプトと行事は、全国に広がっていっていき、「老人の日」に名称を変えました。
そしてその後、1966年に正式に国民祝日として法制化される運びとなった際に、名称が「敬老の日」に改められました。
つまり、市町村などの、地方の行政主導で習慣化され祝日として法制化されたのですね。
この日に、敬老の対象者に贈り物をする市区町村が多いのも、その為なのでしょう。
ちなみに、兵庫県の多可町は山間部に所在する田園が広がるまちで、あの山田錦米の発祥の地でもあるそうです。また、八千代公民館の玄関脇には、敬老の日の発祥地に由来した石碑があります。
なぜ9月なの?
第二次世界大戦後、当時の兵庫県野間谷村の村長さんや村の方たちが、「9月15日にしよう」と決めたと言う事になるのでしょうね。
この地域の主幹産業は農業である訳ですが、「ちょうど休みが取りやすい時期で、暑さの峠を通り越した時期でもあるから」この日に決めた、という話が伝わっています。
加えて、「聖徳太子が大阪四天王寺に、悲田院(身寄りのない老人の救護施設)を作ったことにちなんで」という説や、奈良時代に「元正天皇が親孝行伝説で名高い養老の滝に行幸した日だから」といった説もあるようです。
もしかすると、当時の野間谷村の村長さんや有志の方たちも、これらの伝説を、よくご存知だったのかもしれません。
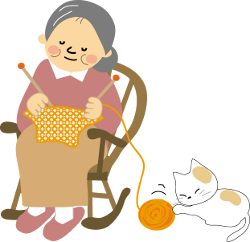
また、以下はあくまで私見ですが。
9月9日には重陽の節句(菊の節句)があり、古来、山間の農村部によっては、栗ご飯などを食べてお祝いした地域もあるそうなのですが、この節句には、長寿を願う意味があったそうです。
ですので、この古来よりの伝統行事が、敬老の日を考案するヒントになったのかもしれない・・・と、個人的に想像しています。
このコンテンツに関連するページ
*本ページの概要・情報は変更される事があります。
By Happie (Updated )



